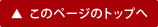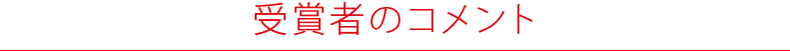


西内 啓 (Hiromu Nishiuchi)
1981年生まれ。東京大学医学部卒(生物統計学専攻)。東京大学大学院医学系研究科医療コミュニケーション学分野助教、大学病院医療情報ネットワーク研究センター副センター長、ダナファーバー/ハーバードがん研究センター客員研究員を経て、現在はデータに基づいて社会にイノベーションを起こすための様々なプロジェクトにおいて調査、分析、システム開発および戦略立案をコンサルティングする。著書に『統計学が最強の学問である』(ダイヤモンド社)、『サラリーマンの悩みのほとんどにはすでに学問的な「答え」が出ている』(マイナビ新書)など。
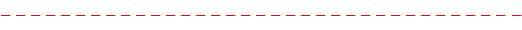
─ビジネス書大賞(経済書部門)の受賞、おめでとうございます。まずはこの本を書こうと思ったきっかけから伺ってよいでしょうか?
ありがとうございます。もはや流行語と言ってもいい「ビッグデータ」ですが、すでに2010年あたりから特集記事は少しずつ出はじめていたんですね。「お! おもしろそうだな」と思ってたまたま一つ読んでみたら、これがまったくおもしろくない。「何を基本的なことを言っているんだ」と(笑)。でも、自分にとっておもしろくないことが世の中の人にとっておもしろいなら、そこには、逆にヒントがあるのかもしれない。
─そのギャップを埋めるのが、あの本だったと。30万部超の大ヒット、相当反響があったのではないですか?
そうですね。一度マーケターの人から冗談混じりに言われたのは、「あれが売れたから仕事にならない」と。一流のマーケターは別として、今まではアンケート調査をしてそれをきれいな円グラフにまとめてクライアントに見せていれば、それで仕事をした感じになっていた人もいたんですよね。でも、マーケターと、彼らに仕事を発注する人を足しても、おそらく日本中で10万人もいないわけです。そこに30万部も売れてしまった。
─なるほど! 依頼する側も、発注を出す側、その予備軍も含めたほとんどのマーケティング関係者が読んで、全員の統計リテラシーが一段あがってしまったと。
だからもっときちんとした分析をやらなければいけないのですが、一体何をやったらいいのかと焦りだしているのが今の状況ではないかと。今執筆中の続編では、そのあたりのより実践的な内容も扱っていこうかと思っています。
─でもこの本が売れるまでは、逆にデータが重視されないもどかしさもあったのではないでしょうか?
それはありましたね。実際にどういうことが起きているかというと、統計的な分析をした結果って、アクションに結びつくまでにたくさんの人を通過していくんです。自分が報告した相手が上司に報告し、さらに上司同士が相談して決定され、現場におりていく。結局その伝言ゲームの中で、一番統計リテラシーの低い人のレベルによって最終的なアクションのクオリティが変わってしまうんですよ。極端な話、途中までみんなでやろうやろうって盛り上がっていても現場に分析結果と指示がおりてきたときに「何だこれ意味わかんねえ」となったり。逆に偉い人が、「分析のことはよくわからないが、おれの経験ではそれは違う」と言い出したり(笑)。
─ビジネスの世界は、まだまだ数字で動いていなかったと。では、西内さんから見て、これから特に統計を必要とする分野はどこでしょう?
日本の製造業にはとっくに統計学が行き渡っているんですよ。工場では、いかに品質を上げつつコストを下げるかについて当たり前のように専門用語を使った議論がなされている。逆にまだやっていない分野ほどリターンは大きいですね。統計の応用事例ってマーケティングだけが注目されがちですが、たとえば人事にだって適用可能です。
─人事、ですか?
実はどういうタイプのリーダーとどういうタイプの業務が相性がいいのかについては、定量的に分析された研究がもうあります。ほかにも、どういう要素が従業員のモチベーションやパフォーマンスに影響するのか、というのも、すでに研究されています。それこそ、新卒者の採用基準だって謎ですよね。多くの企業が採ろうとしている人材は、簡単に言うとSPIが高くて面接でハキハキとコミュニケーションが取れる若者ですが、SPIというのは一般知能と特殊知能でいうと、主に一般知能だけを測るもの。おおざっぱに言えば「どの仕事もある程度そつなくこなせるか」という基準でしかない。その一次元だけだと、一番上の子が採れなかったら、「しょうがないからもう少し下の子を採ろう」みたいなことになってしまう。でも、「うちでは一般知能よりもこの能力が重要だ」という基準が明らかになっていたら、簡単にそういう人材を集められるかもしれません。
映画『マネーボール』でもありましたけど、みんなホームランを打てる人を採ろうとするんですよ。フォアボールで塁に出るのがうまい人は、あまり注目されない。みんなあれを映画の中の話と思っているけど、ビジネス全般に使えるはずです。面接にしても、組織や業務によってはいわゆるコミュニケーション能力より大事なものがあります。仕事によってそれぞれ求められる能力は違うのに、一次元の基準で測ろうとするから、結局多くの人が幸せになれない。
─なるほど、西内さんの問題意識がだんだんわかってきました。
人間の行動を、データによって明らかにするというのが自分の本業なんです。もちろん、行動を明らかにして終わりではなく、それをいい方に変えるというところまで込みで。本来、統計学と行動科学はつながっているべきなんですよ。当たり前ですが、ビッグデータだけ扱えても、それをアクションに落とし込んで人の行動や選択を変えない限り意味はありませんから。今、自分が仕事をできているのは、その両方が扱えるからです。ただ、統計学と行動科学のように学問と学問をつなぐだけじゃなく、今はまだ学問の世界と、ビジネスをはじめとした実社会の間もうまくつなげられていない部分があります。そこをいったりきたりして埋めていくのが、自分の役割かなと思っています。
─最後に、まだこの本を読んでいない方に一言メッセージを
望むと望まざるとにかかわらず、ぼくたちの生活にはすでにデータが入ってきています。そして、それを「わからないから拒否する」ということはだんだんと許されなくなってきている。逆に早い段階から慣れ親しんでおけば、ビジネス以外でも、たとえば「子を持つ親」や、「消費者」という立場においても、いろいろと自分の人生を有利な側に傾けてくれるのではないかと思います。この機会に乗り遅れないでください。すでに30万人が読んでいますから(笑)。