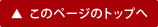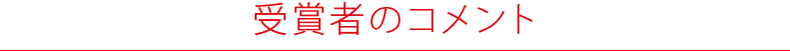

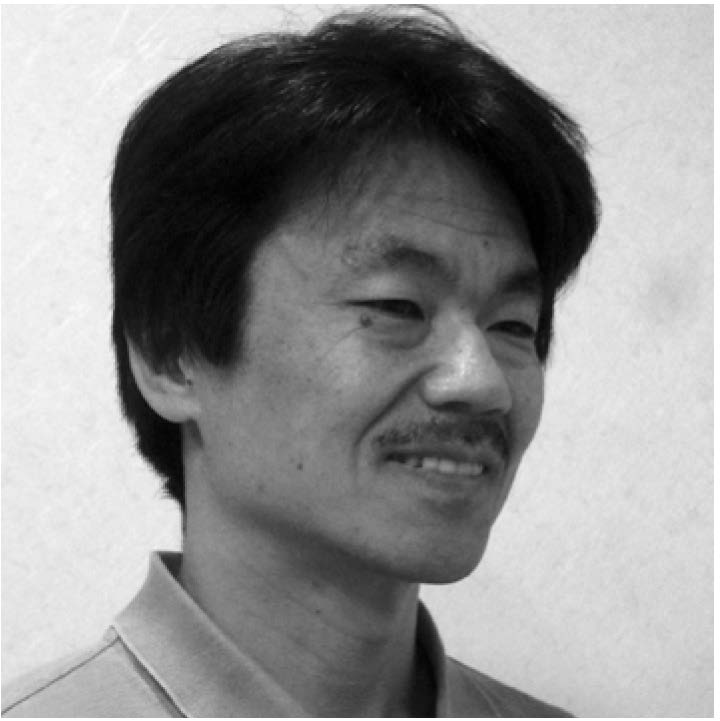
三谷 宏治 (Koji Mitani)
1964年生まれ。東京大学卒業後、ボストンコンサルティンググループ、及びアクセンチュアで19年半、経営戦略コンサルタントとして働く。2006年から教育の世界に転じ、07年からK.I.T.(金沢工業大学)虎ノ門大学院 教授に。同時に、子どもたち・親たち・教員向けの授業や講演に全国を飛び回る。テーマは「決める力」「発想力」と「生きる力」。著書多数。早稲田大学ビジネススクール・グロービス経営大学院の客員教授、放課後NPOアフタースクール・NPO 3keysの理事、永平寺ふるさと大使を務める。
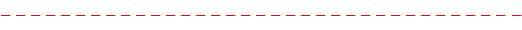
─経営書部門での大賞の受賞、おめでとうございます。今日はまず、この本が生まれたきっかけからお伺いしていいですか?
ありがとうございます。まず、ご存知のように書店には経営に関する本はたくさんありますよね。でも、ほとんどの経営書には「おもしろさ」の要素がたりないんです。本来、すべての本は楽しいもののはず。どんなジャンルの本だって、楽しくなければ読み進められないし、読み進められなければ、当然学びもない。だから、真に学びを提供しようと思えば、それはおもしろくなければいけないんです。
─経営書であってもおもしろくあるべきだ、と。
ええ。だから、ディスカヴァーの社長である干場さんとお話して、デザインも含め“ROCK”な経営書を創りましょう、ということになりました。そして、おもしろくするためには、単なる情報の羅列ではなく、「ストーリー」にする必要がありました。時間軸の流れに沿って、背景とつながりで経営戦略を語るという方針は、そんなところから決まりました。
─確かに、読んでいて、今までバラバラにつまみ食いしてきた経営の知識が、一連の流れとしてつながっていく快感がありました。こんな時代背景だったからこうした経営の思想が出てきた、という部分まで踏み込んでいるから、とにかく頭に入ってきます。
今までは、学者が書いた学術的な経営書か、コンサルタントがリアルな例をまとめあげた経営書か、どちらかが多かったですよね。だけど、経営理論そのものは、学者と、コンサルタント、そして事業家の三者全員がつくりあげてきたものです。私としては、コンサルタントとして見てきた世界もあるし、MBA(INSEAD)で見た学者の世界もあるし、実際に事業をつくってきた事業家として見た世界もある。すべての視点から、なるべくバランスの良い経営書をつくりたかったんです。
─審査員からは、この本の圧倒的な情報の密度に「この本を一人の人がつくったことが驚きだ」という声が挙がっていました。普段は、どんな情報に触れていらっしゃるんですか?
いたって普通ですよ。日経新聞に、日経ビジネス、週刊東洋経済やダイヤモンドなどの雑誌。特にフォーブスを普段から読んでいたり、ということもない。ただ、読みながら常に二つのことをやっています。一つは、過去とつなげること。たとえば、「ある会社の経営方針が悪い」という記事があったときに「でも半年前には良い経営だって書かれていたよな」と、つなげられるかどうか。もう一つは、抽象化して覚えておくこと。単に「クックパッドが有料会員で高収益」ではなくて「有料会員では儲からないという常識を打ち破った例」として覚えると、抽象度が一つ上がる。そうして記憶しておくことで、過去ともつながりやすくなる。こういった力を使って、この『経営戦略全史』を書いた、とも言えるでしょうね。
─本の後半では、Google のエリック・シュミットをはじめ、まさに今、リアルタイムで経営戦略の歴史を更新し続けている経営者にも触れられていました。三谷さんから見て、他にも注目すべき経営者はいらっしゃいますか?
今注目しているのは、中国の「ネット三國志」ですね。ネット通販最大手、阿里巴巴(アリババ)のジャック・マー。百度(バイドゥ)のロビン・リー。そして、テンセントのポニー・マー。全員40代です。時価総額12兆円を超えるような規模の企業が、今中国を足がかりに世界に出て行こうとしている。未だ日本人には注目されていませんが、非常に大きな可能性を秘めていると思います。もっとも、このうち1~2社は崩壊するかもしれませんが。
あとはやっぱりクリス・アンダーソン。彼の『ロングテール』『フリー』『MAKERS』はいずれも傑作ですが、実はどれも同じことを言っています。マイナーなもの、「小さき者」にチャンスがある、ということです。
今、世界のビジネス界で起こっているのは巨人同士の陣取り合戦です。Google、Amazon、Apple、それにfacebookや阿里巴巴、百度、テンセントなど。しかしその一方で、かつてないほどに「個人」にも世界が開かれています。どんなに無名でも、おもしろいアイデアとビデオ一発で数千万円の投資が、クラウド・ファンディングによって集まるのです。巨人同士の闘いになっていることも事実ですが、かといって巨人しか闘えないわけじゃない。これはかつてなかったことです。個人や零細事業者といった「小さき者」たちにも大きなチャンスがある時代なのです。
─規模以外にも、変化している点はありますか?
会社を構成するのは「ヒト・モノ・カネ」と言われますが、すべての部分がIT化しています。ヒトやモノはクラウド・ソーシングで調達。カネも先ほどお話したクラウド・ファンディングで調達できる。あらゆるものがネットワーク化され、複雑で幅広くなってきているとも言えますね。これまでは「会社とお客さん」に分かれていたのが、今では「お客さんを商品開発に巻き込む」とか「無料客にもちゃんとサービスする」とか、とても複雑になってきています。
そんな組み合わせ(=ビジネスモデル)自体は無限にあるから、それをうまく合わせることで新しいビジネスがいくらでも生まれてきます。特にシリコンバレーでは。それに、意外と日本は、そういうことがやりやすい場所かもしれません。眠っているリソースがいっぱいありますから。家にいるけど高い技術を持つ女性も多くいるし、会社の中にだってハイスキルの人たちが結構眠っている。そういう人たちが世界にでて活躍できる社会にしよう!というのが今執筆中の続編『ビジネスモデル全史』の結論になりそうです。
─経営戦略に続き、ビジネスモデルですか! これも「経営戦略」と同じく、わかったようでよくわからない言葉です。読める日が来るのを、心待ちにしています。