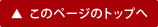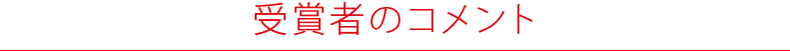


リンダ・グラットン (Lynda Gratton)
ロンドン・ビジネススクール教授。経営組織論の世界的権威で、英タイムズ紙の選ぶ「世界のトップビジネス思想家15人」のひとり。ファイナンシャルタイムズでは「今後10年で未来に最もインパクトを与えるビジネス理論家」と賞され、英エコノミスト誌の「仕事の未来を予測する識者トップ200人」に選ばれている。組織におけるイノベーションを促進するホットスポッツムーブメントの創始者。『Hot Spots』『Glow』『Living Strategy』など7冊の著作は、計20ヶ国語以上に翻訳されている。人事、組織活性化のエキスパートとして欧米、アジアのグローバル企業に対してアドバイスを行う。
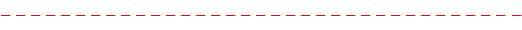
ビジネス書大賞の受賞を大変光栄に思います。私は『ワーク・シフト』を世界中の人々が未来に何が待ち受けているかについてより深く理解したうえで、より情熱を感じ、充実感を得られる働き方をする一助となるようにと願って書きました。本書が日本で大きな反響を呼んだことをとてもうれしく思っています。今年の二月に訪日し、多くの方と話をしましたが、この本のテーマがまさに日本の置かれた状況に合ったものであると実感しました。
本のなかでは、これから世界を大きく変えていく要因について述べました。グローバル化によって市場がどんどん開放されていきます。技術革新が今まで想像できなかったようなやりかたで人々や知識を結び付けていきます。日本のような先進国の出生率が急減して人口構成が変化する一方で、著しい長寿化が進行します。そして、天然資源や環境の問題もあります。未来の世界を形づくるこれらの要因によって、日本の社会がとりわけ大きな影響を受けることは明らかです。
この本を書いたときの私の関心は、こうした世界の変化に対して個人がどのように備えたらよいのか、というものでした。今回の訪日中に感じたことを、帰国後、日本の若者へのメッセージとして書きました(『ワーク・シフト』著者から日本のY世代へ「視野を広げ、発言し、行動せよ」)という記事にまとめました(プレジデントオンライン http://president.jp/articles/-/8827 )。そこでも述べていることですが、この本がここまで日本の方々に受け入れられた理由は二つあると思います。
一つには、日本のような(もちろんイギリスも) 先進国の若者は、いろいろな意味において、世界のあり方を変えるこれらの要因の震源地にいるということです。彼らが自分たちの将来のキャリアを考えるとき、親が経験したような予測可能な会社員としてのキャリアパスはもはや望めません。しかしその代わりになるものについてもはっきりと見えていない。
『ワーク・シフト』が日本の若い層を中心に読まれたのは、 本書が具体的な未来の姿を描いているからでしょう。私は領域の狭いスペシャリストを志向するよりも、領域を超えた連続スペシャリストを志向すべきであると書きました。また、自分の働き方を会社に委ねるのではなく、自分自身で決めることの大切さについても説きました。私がもっとも伝えたかったのは、「親=会社、子=社員」という親子関係から、「会社=大人、社員=大人」という大人同士の関係への脱却が必要であるということです。
日本で私の本が受け入れられたもう一つの理由は、社会構造の変化です。日本のような成熟した国では、 伝統的な家長を頂点とした大家族が核家化、人口移動、経済的圧力によって崩壊しています。その一方で、新たな関係性やネットワークが生まれています。『ワーク・シフト』では、未来に必要となる三つのタイプのネットワークについて書きました。声をかければすぐに力になってくれる頼れる仲間たちから成る「ポッセ」、斬新なアイデアをもたらしてくれる、少し離れたところにいる知り合い(もしくはその知り合い)から成る「ビッグアイデア・クラウド」、そして心からくつろいで一緒に過ごせる親しい人たちから成る「自己再生のコミュニティ」です。こうしたネットワークづくりにおいても重要なのは、どのような働き方をしていきたいのか、個人が主体となって考えていくことです。
本を書くとき、私は書斎にこもって膨大な時間を構想と執筆に費やしますが、書いている最中には、自分の本がどんな人に読まれるのか、自分の書いた本がどんな人の人生に影響を与えるのか、想像だにできないものです。今回このような賞をいただけたことはこのうえもない名誉であり、喜びです。ロンドンの書斎で綴られた文章がこれほど多くの日本の読者に届いたということじたい、グローバリゼーションの意味や、未来について考えることの大切さを物語っているのだと思います。