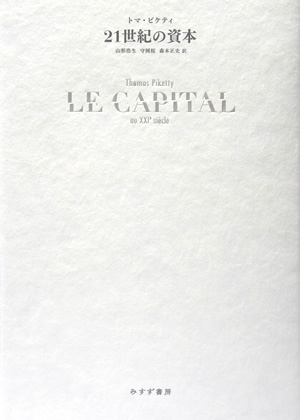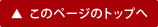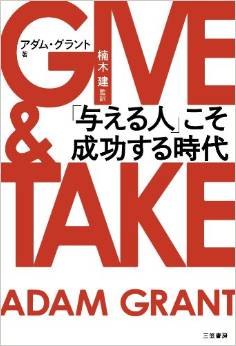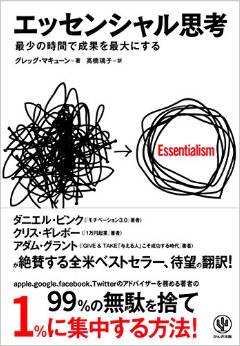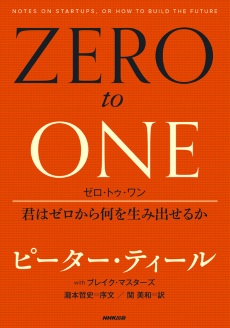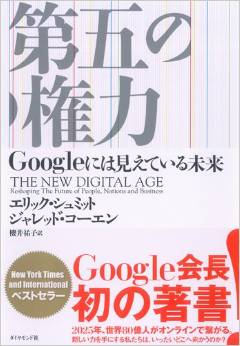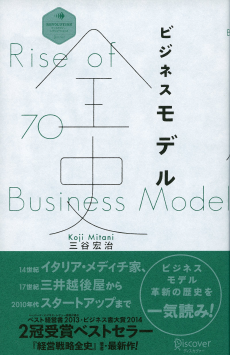あれだけの大著がブームになるのは好ましい現象だと思った。日本もまだ捨てたものではない。著者のはっきりした論調も清清しい。
亀井史夫さん/KADOKAWA 角川書店
発売前からメディアで度々取り上げられ解説書やピケティ特集の雑誌なども売れ続けています。資本収益率が経済成長を上回り格差がより拡大していく、格差の拡大が中東におけるテロなど社会を不安定にし民主主義に危機をもたらすという主張はとても共感できました。この本は資本主義経済における富の分配と格差についてたくさんの人たちが考えるきっかけになったと思います。
鈴木寛之さん/八重洲ブックセンター
膨大なデータと明晰な理論によってにより、これまでの「経済成長によって所得格差は縮小する」とされていた経済学の常識を覆すキッカケとなった。世界中に大きな衝撃と議論を巻き起こした本書は、ポール・クルーグマン氏(プリンストン大学教授)が「本年で、いや、この10年で、最も重要な経済学書になると言っても過言ではない」と述べているように、格差の問題を捉える上で、重要な本となるであろう。
小笠原真奈武さん/ビジネス書のエッセンスNeo
2014年発行の最も印象深い本を問われれば、迷うことなく『21世紀の資本』と答えます。経済学の分野でここまで話題をさらっていく本も珍しい。賛否両論あるにせよ、無視はできない論文です。
桑原勇太さん/紀伊國屋書店
一大ピケティブームを巻き起こした本書。分厚い経済の専門書が飛ぶように売れたのは、資本主義と広がる格差という同書のテーマを、私たちが自分事として捉えてからに他なりません。読者・時代のニーズに応えたこの経済の専門書は、2015年を代表する1冊であると思います。
中島万里さん/TSUTAYA
みんながうすうすそうじゃないかと思っていたことを、最新の技術と理論を駆使して立証してくれたヒーローとして、ピケティの登場は経済学の専門家だけでなく広く一般に歓迎された。書店員として、予想以上の反響に引きずられっぱなしだった。この手ごたえは、忘れられない。
野上由人さん/リブロ
格差問題に一石を投じる書籍。世界的に読まれているということだけでなく、アベノミクスに疑問を呈するためにも活用できる改革の書。
山中勇樹さん/コジゲン
格差問題や経済政策、国民国家と資本主義を考えるにあたって新たな世界基準を示した本。
唐沢暁久さん/講談社
ペンシルベニア大学ウォートン校で組織心理学の教鞭をとる筆者は、人と人との関係における「ギバー(人に惜しみなく与える人)」、「テイカー(真っ先に自分の利益を優先させる人)」、「マッチャー(損得のバランスを考える人)」のそれぞれの特徴と周囲に与える影響を、様々な具体的事例をもとに分析している。そして、他者利益と同時に自己利益にも関心を持つ「他者志向のギバー」となることを勧めている。価値の“奪い合い”や“交換”ではなく、“恩送り”(pay forward)を実現することにより、自分を取り巻くコミュニティやネットワーク全体の価値を大きく成
長させていくことができる。この考え方は、企業活動を営むにあたって大いに共感できる。(一部省略)
泉谷直木さん/アサヒグループホールディングス株式会社
2013年の話題作『嫌われる勇気』と合わせて読むと、より面白い。単に「他人に貢献する人が成功しますよ」というスピリチュアルか説教のような内容ではなく、「ただ与え続けるだけの人は他人に利用され成功できない」など現実的なことも書かれているほか事例も豊富で、説得力がある。人間には3つのタイプがあり、ギバー(人に惜しみなく与える人)、テイカー(真っ先に自分の利益を優先させる人)、マッチャー(損得のバランスを考える人)の3つのパターンがあると著者は言う。その特徴や事例を読んでいると、「自分はどのタイプだろう」「あぁ、これは◯◯さんだ」など、知人の顔やエピソードが思い出される。 特に面白いのは「テイカーが成功すると妬まれるが、ギバーが成功すると喜ばれる」という話。自分の利益を一番に考えるテイカーが勝った時はたいてい誰かが負けるが、全体の価値を増やすことを考えるギバーが成功したときは周りにもメリットがあるからだ。 自分の考えを改めるためにも、また人付き合いを見直すためにも、読んでおきたい一冊だ。
洞野宏介さん/ライフハックブログKo's Style
著者は人間を、ギバー(与える人)、テイカー(受け取る人)、マッチャー(バランスをとる人) の3タイプに分類。「ギバーこそ成功する時代」という事を、行動科学の理論と実証研究に裏打ちされた豊富なデータで解説している。 読むとビジネスに役立つだけでなく「自分も与えるようになろう」と心が豊かになる一冊。
せんちえ慶次さん/せんちえ
他者から受け取ろうとする「テイカー」、バランスを取ろうとする「マッチャー」、そして、与えようとする「ギバー」。ギバーがどれだけ成功するか、が、科学的に述べられている。たしかに、身の回りにいるギバーは、いるだけで周りが幸せになるし、実際に仕事ができる人だ。自己啓発書はあまり読まないのだが、納得してしまった。
竹添嘉子さん/紀伊國屋書店
プロダクトの作り方、スマートクリエイティブと呼ばれる人材をどう採用し、マネジメントするのからGoogleの具体的なエピソードを交えて書かれていたので、とても楽しく読めた。
吉岡諒さん/ウィルゲート
インターネットの王者Googleを知るための一冊。インターネットを使ったことがある人、つまりほとんどすべての人にとって必読の書。
山中勇樹さん/コジゲン
グーグルに関する書籍は何冊も出ているが、本書は今まで描かれておらず知りたかったマネジメントに関する事を中心に描かれており、グーグルの本当の強さを改めて知ることが出来た。
昼間匠さん/リブロ
忙しすぎる毎日において、なにをやめるか?を明確に考え直させる本であるとおもう。方法論だけでは無く、考え方としてどうするのか?そのあたりをもう一度見直すきっかけになった。
丸山純孝さん/エンジニアがビジネス書を斬る
どの業種のビジネスマンにもオススメますし、やるべきことの優先順位を誤り、人生を阻害することもある思考を、より豊かな人生形成のための思考に導いてくれる書籍です。個人的に年間400冊ほどビジネス書籍を読ませていただきますが、去年の1番はこの書籍でした。
荒木泰大さん/フリーランス
情報過多の中で、イノベーションを起こし、クリエティブに働き暮らすには、選択と集中が必要であるとシンプルに力強く真実を伝えている。
米田智彦さん/ライフハッカー[日本版]
翻訳書の為、読みにくいと思いきやさまざまな職種や立場の人のエピソードが具体的に語られており非常に受け入れやすく、自分自身の働き方を見つめな直すには最適な1冊でした。
昼間匠さん/リブロ
自分の本当に大事なことを選択し、それに集中する。これまで何度も言われてきたことではあるけれども、絶妙に織り交ぜられるエピソードととも読み進めることで改めて納得させられる部分も多く、仕事のみならず、人生についても見つめ直すきっかけとなる1冊だと思います。
中島万里さん/TSUTAYA
本書は、多くの選択肢にあふれたなかで生活している現代の状況を捉え、その中で本質を見極め、本当に価値あるものにエネルギーを注ぐ重要性を説いている。「忙しい」と嘆く現代人にとって、一度は読むべき必読の書。
小笠原真奈武さん/ビジネス書のエッセンスNeo
こんがらがった頭を整理してくれる思考の整理術。気持ちよく仕事をするためのヒントが詰まっています。
江口裕人さん/扶桑社
人生を重ねると、今までやってきた習慣・思考法・ものの見方が偏ったり、ある一方向で固まってしまったりする。当たり前だと思っていることが実は非エッセンシャル思考であることに気づかされ、必要なことに集中するには無価値なノイズを削除して重要なことを見極めなければならないと教えてくれる。『7つの習慣』にも通じるが、自分に必要な思考の整理を改めて別の切り口から考えさせてくれる1冊。
北野有希子さん/MPD
これまで門外不出だった「京セラフィロソフィ手帳」を、京セラの創業者、稲盛和夫氏が解説しています。 京セラの哲学、京セラが大切にしていること。そしてなぜそれが大切なのか。ビジネス、経営、仕事において何が大切なのか。これがわかる本です。繰り返し読み返して、自分の考えや行動を改善するために使いたい本です。
こばやしただあきさん/「知識をチカラに!」ビジネス書書評メルマガブログ
自らを一技術者と語る著者が会社をよくするためにひたすら社員へ説いたという、考え方と気持ちを「共有する・ベクトルを合わせる」ことの大切さがやがて「アメーバ経営」を創りあげる原点であったというのが興味深い。 常に正しい行いを自らに課す京セラフィロソフィは、一種の戒律であるとも書かれているが、特に本書はカバーを外した姿も美しい。紺地に潔い金文字の佇まいは、そのストイックなまでの内容と共にバイブルと呼ぶにふさわしい。
福田浩子さん/ジュンク堂書店
数年前に日本中を席巻した「もしドラ」ブームは、経営に大切な要素"ひたむき"を再認識させてくれました。この「京セラフィロソフィ」はまさに"ひたむき"の塊のような本です。分厚い一冊ですが、柔らかな文体で綴られる幅広いエピソードはどなたにも優しく響きます。子どものような純粋さと、自らを決して甘やかさない厳しさで突き進む経営哲学に触れ、緩んでなどいられないぞと一段階ギアが上がる思いがします。
成田すず/ジュンク堂書店
門外不出の書と言われ、やっと発売になった本書は、稲盛氏のすべてがここに詰まっていたのだと実感する一冊です。会社をより良くするための指針が示されていても、それを実行できるかにかかっていると問われていることに気づいた時に、とても身が引き締まる思いがします。
水上紗央里さん/紀伊國屋書店
稲盛氏の著書は本年も数多く出版され、どれも愛読しているが、若干内容が類似してきている感がする。その中ではこの書が読みごたえがあった。
前田邦雄さん/ヤマトマシナリー
盛和塾の生徒と京セラ社員にのみ配布されていたという門外不出の一冊のまさかの書籍化。今まで数多くの書籍が世に出てきたが、この本がそれらすべての原点ともいえる一冊。すぐに実践できて効果のある具体的なハウツー本ではない、しかも価格も安くはない。それでもこれだけ多くの人が注目し、手に取り、ブームを巻き起こす。この本の価値を多くの人が感じている証拠だと思う。人として正しいことは何か、という原点的な問いに対する稲盛流の考えは、経営者のみならず、これから社会に出る世代の人にも知ってほしいと思う。稲盛氏の書籍を多く読み進めてきた方にとっては集大成の一冊。初めて読む方にはまさにはじめの一歩となる一冊だと思う。600ページという内容の濃さ重さに加え、装丁も稲盛氏自身の希望を忠実に反映したものだと聞いた。この一年で重要であるのはもちろん、今後も長く、大切に売っていきたい、と思わせる本である。
黒田紗穂さん/紀伊國屋書店
いまどき流行しているリーンスタートアップやピボットではなく、他社を凌駕する高度な技術で、小さな市場を独占することからはじめること等、多数ある起業やイノベーション関連の書籍の中でも主張が特徴的で刺激に富む。
松尾茂さん/ブログ TravelBookCafe
起業家というものを考えるに際して参考になる記述がたくさんある。示唆に富んだ内容はくり返し読む価値がある。
山中勇樹さん/コジゲン
「ビジネスに同じ瞬間は二度とない」という言葉のもと、リスクを選び目的志向を持って生きる人生を推奨しています。事業の創業者の重要な仕事は、初めにやるべきことを正しく行うことであり、土台に欠陥があっては偉大な企業を築くことはできないということを訴えてるのが印象的でした。これからの未来を描いて、著者の言う「隠れた真実」を見つけ出したくなってきます。
北野有希子さん/MPD
オンライン決済サービスのペイパル(PayPal)の共同創業者ピーター・ティールが、母校スタンフォード大学で行った講義の書籍化。逆張りの天才の面目躍如で、1からnを生み出す水平的進歩ではなく、ゼロから1を生み出す垂直的進歩とは何かについての独特の持論を展開している。一言で言えば、グローバリゼーションが水平的進歩で、テクノロジーが垂直的進歩だということ。殆どの人はグローバリゼーションが世界の未来を左右する大きな事象だと思っているが、著者によれば、テクノロジーの方が人類にとって遥かに重要であり、新たなテクノロジーなしにはグローバリゼーションは持続不可能である。そして、テクノロジーは何もIT分野だけに限られた話ではなく、確かに20世紀後半以降、劇的に進化したテクノロジーはコンピューターと通信だけだったのでITが全てのように見えてしまうが、それ以外の分野で新たなテクノロジーを創造することが自分達に課せられた使命なのだと言っている。実際、著者を始めとした「ペイパル・マフィア」は、ユーチューブ(YouTube)、テスラ・モーターズ、スペースX、イェルプ(Yelp!)、ヤマー(Yammer)など、数多くの革新的企業を立ち上げてきた。
著者が繰り返し強調するのは、新しいビジネスは、競合相手が存在せず市場を圧倒的に独占できる全く新しいコンセプトを持って始めろということ。企業間競争には批判的で、企業は競争に明け暮れる結果、目先の利益に追われ、長期的な未来に対する備えができなくなってしまうので、独占こそが重要なのだと言っている。つまり、何年にも亘って独占的利益を保証されることがイノベーションのインセンティブになり、それが企業の進歩をもたらすのであり、独占は全ての企業にとって成功の条件であるとまで言い切っている。皆が信じる「競争」は、アメリカ人の思考を歪めている単なる「イデオロギー」であり、「競争」という強迫観念に駆られたアメリカの教育制度に対しても大変手厳しい。飛び抜けて優秀な学生にとっては、学校は集中すべき活動に割くための時間を奪い、ありふれた活動の場しか与えない有害な存在であり、経営コンサルタントや弁護士やインベストメントバンカーになっても単にキャリアとしての可能性の幅を広げて小さな成功につながるだけで、皆と同じ人間になるために年間何万ドルも払って大学に行くなんて止めろと批判している。つまり、学校教育は具体的なヴィジョンを持てない者が曖昧な将来に備えるために仕方なく行くためのもので、やりたいことがハッキリしている者にとっては意味がないということである。
皆が著者のような生き方を選択できるかどうかは別として、あらゆる常識を明快に切って捨てる著者の主張の切れ味は、一度味わってみるべきである。
堀内勉さん/森ビル
ペイパルの共同創業者でエンジェル投資家としてもっとも注目されている投資家のひとり、ピーター・ティール氏によるベンチャー起業家へのアドバイスです、人類の未来が絶滅か進歩かは目の前のチャンスをつかみ新たなテクノロジーを、生み出せすことができるかにかかっている未来に向かって邁進するアメリカの起業家精神がとても強く印象に残りました。
鈴木寛之さん/八重洲ブックセンター
小さな市場で独占せよという部分がとても感銘を受けた。今の日本の風潮に一考を投じた作品だと思った。
無記名/千代田区立図書館利用者
冒頭で描かれる、まるでSF映画の様な未来。仮想世界と現実世界の2つの世界を生きるような未来像は、確実に現実のものになってきている。オンラインの自由さは、逆に不自由にもなり得るのだが、Google会長の著者が描く未来は、それでも明るい。「権力」をどう使うかは、これからの私たち次第だから。時代を反映する1冊。
竹添嘉子さん/紀伊國屋書店
最近はマスコミ批判が激しいが携帯電話の普及でたくさんの人の発言が広く伝達され影響力を持った為で、市民が第五の権力を手に入れたからだろう この本はグーグル会長がインターネットの普及した未来について語っています。仮想世界と現実世界、2つの世界をどう生きていくか、いまから準備する必要性を強く感じました。
鈴木寛之さん/八重洲ブックセンター
100社、100名として教科書的になっていないのが良い。ビジネスモデルがストーリーで平易に語られ、密度も濃い。三井越後屋の例が新鮮だった。海外と日本の事例バランスもよい。
無記名/アカデミーヒルズライブラリー会員
前作の経営戦略全史に続き、遠い昔まで遡りビジネスモデルを整理した力作。「ビジネスモデルとは何か」を俯瞰して考えるために役立つ事例が、体系的に、かつわかりやすく書かれていて、経営書にありがちな退屈さをまったく感じなかった。事例に出てくる企業は我々にもなじみの深いものが多いが、これからはいつもと違う視点で見ることができそうだ。これまで、ビジネスモデルという言葉を食わず嫌いしてきた方におすすめしたい。前作同様いつまでも本棚においておきたくなる一冊。
匿名